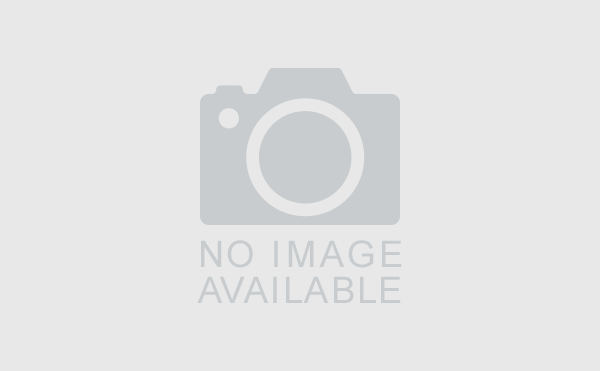「代わりに契約しといて」が命取り?「表見代理」という名の地雷
## 第5回: 「代わりに契約しといて」が命取り?「表見代理」という名の地雷
スタートアップ「ビジラボ」の日常は、常に時間との戦いだ。俺、青木健一は、社長として、営業として、そして時に雑用係として、日々を駆け抜けている。前回の「権利能力」や「行為能力」の話で、契約の「主体」がどれほど重要か骨身に染みたばかりだ。未成年との契約が、どれほどリスキーか。俺はもう、そんな初歩的なミスはしないと心に決めていた、はずだった…。
1. ストーリー:「俺の片腕」に任せすぎた結果…?
セクション1: 問題の発生と絶望(導入部)
「うおおおおお、ヤバい、時間が全然足りねぇ!」東京、恵比寿のインキュベーションオフィスの一角。ビジラボのオフィスには、今日も熱気と、俺の悲鳴が充満していた。創業から数ヶ月。俺たちのAIを活用した営業支援SaaSは予想以上の反響を呼び、ユーザー数は順調に伸びている。エンジニアの田中は、その対応で深夜までモニターと睨めっこ。経理・総務を一人でこなす斉藤は、山のような請求書と格闘している。俺は俺で、新規顧客の開拓、投資家へのピッチ資料作成、さらにはチームマネジメントと、一日24時間じゃ全く足りなかった。
「社長、このサービス利用規約の変更、いつまでにチェックしますか?ユーザーへの告知も間に合わなくなりますよ」
斉藤の声に、俺はキーボードを叩く手を止めた。ディスプレイには、まだ手付かずの契約書がずらりと並んでいる。 「う、うぐぐ…。斉藤、悪いんだけど、そこ、ちょっと目を通しといてくれる?俺、これから大事な打ち合わせで…」 「え、私ですか?でも、これ、社長の最終確認が必要な重要案件では…」 斉藤が困ったように言う。その通りだ。サービス利用規約は、ユーザーとの間で交わされる契約書の根幹。先日、神崎さんに「『消費者契約法』や『定型約款』は、BtoCサービスでは特に重要ですよ」と釘を刺されたばかりだ。俺だって、ちゃんと目を通したい。だけど、本当に時間がなかった。
「頼む!斉藤!お前しかいないんだ!俺の『片腕』だろ?細かいところは任せるから、問題なさそうだったら、もう進めてくれ!最悪、何かあったら、俺が責任取るから!」 俺は、勢い任せにそう言って、焦る気持ちを抑えきれずにオフィスを飛び出した。斉斉藤は呆れたような顔で、溜息を一つ吐いていたが、俺は振り返らなかった。この時、俺は心の中で「まあ、斉藤なら大丈夫だろ。しっかり者だし」と安易に考えていたんだ。
数時間後。打ち合わせを終えてオフィスに戻ると、斉藤が不安そうな顔で俺を待っていた。 「社長…すみません、いくつか確認したいことがあって…」 「ん?どうした、斉藤?利用規約のチェック、終わったか?」 「いえ、それが…」 斉藤の様子がいつもと違う。いや、むしろいつも通りの「何かマズいことが起きている」雰囲気がプンプンしている。俺は嫌な予感がして、ゴクリと唾を飲んだ。
「その前に、先ほど届いたこの書類なんですが…」 斉藤が差し出したのは、新しいオフィスビルの賃貸借契約書だった。ビジラボは順調に拡大しており、手狭になった今のインキュベーションオフィスから、自前のオフィスに移転する計画が進んでいたのだ。 「これは俺が確認するつもりだった書類じゃないか!まだサインもしてないし、条件交渉も途中だったはずだぞ?」 俺は青ざめた。賃貸借契約は、ビジラボにとって新たな大きな固定費となる。その交渉は俺が責任を持って進めていた。しかし、その契約書には、既に斉藤のサインが、俺の代理として書かれていたのだ。 「え…?斉藤、これ、どういうことだ?」 「すみません社長。先ほど、大家さんが『本日中に契約しないと、他に希望者がいる』と言ってきて…。社長が『片腕だから任せる』と仰ったので、私が…」 斉藤は真っ青な顔でうつむいた。俺は頭が真っ白になった。 「いや、俺は『利用規約のチェック』を頼んだんだ!オフィス契約のサインをしろなんて、一言も言ってないぞ!」 「ですが、社長は『問題なさそうだったら、もう進めてくれ』と…。それに『最悪、何かあったら、俺が責任取るから!』とも…」 斉藤の震える声に、俺は絶句した。確かに、そんなことも言った。しかし、それはあくまで利用規約の変更の話であって、何千万もする賃貸借契約のことではない。 「う、嘘だろ…?」 契約書に目を落とすと、そこにはいくつかの不利な条件が盛り込まれている。保証金の返還率が低く設定されていたり、原状回復費用が異常に高かったり。俺が交渉でなんとかしようとしていた部分が、全て相手の言いなりになっていた。 俺は、目の前が真っ暗になった。俺の軽率な一言が、会社に何千万もの負担を負わせる契約を成立させてしまったのか?
その時、背後から冷静な声がした。 「青木さん、これはまずいですね。『代理』の問題と、『表見代理』のリスクが同時に発生しています」 振り向くと、そこに神崎さんが立っていた。相変わらず、涼しい顔で、しかしその視線は鋭く、俺の心臓を鷲掴みにするようだった。
セクション2: メンターの登場と用語の提示(展開部)
「か、神崎さん!聞いてくださいよ!斉藤が勝手にオフィス契約にサインしちゃって!俺、そんなこと頼んでないのに!」 俺は半ばパニック状態で神崎さんに訴えた。斉藤は顔面蒼白で俯いている。 神崎さんは俺の剣幕にも動じず、冷静に契約書に目を通した。 「青木さん、斉藤さんが言っていることは事実ですね。あなたが『最悪、何かあったら、私が責任を取る』と発言した、と。そして斉藤さんに『任せる』と伝えた、と」 「そ、それはそうっすけど!でも、それは利用規約の話で…」 「ええ。ですが、相手方(大家さん)から見れば、あなたが斉藤さんに『代理権』を与えた、と認識してしまう可能性があります。そして、その『代理』というものが、実は非常に深い罠を抱えているのです」 神崎さんの言葉に、俺は背筋が凍った。深い罠? 「確かに、青木さんの意図とは異なる結果になったのでしょう。しかし、法的に見れば、会社がこの契約に縛られる可能性は十分あります。特に、あなたが斉藤さんに『何でも任せる』というような態度を普段から示していれば、なおさらです」 「え、何でもって…」 俺は普段から「斉藤、これ、頼む!」「斉藤、あれも頼む!」と、あらゆる雑務や手続きを斉藤に依頼していた。斉藤は優秀だし、俺の右腕だと本気で思っていたからだ。だけど、それが仇となるなんて。 「青木さん、あなたは斉藤さんに『代理権』を与えたつもりはなくても、相手方から見れば『代理権を与えた』と信じるに足る状況を作ってしまった。これが、今日のテーマである『表見代理』という概念です」 「ひょ、表見代理…?」 初めて聞く言葉に、俺は混乱した。代理ってのは、代わりに何かをやってもらうってことだろ?俺は頼んだ覚えないのに、何で責任を取らされるんだ?神崎さんは、そんな俺の疑問を正確に見抜いたように、ゆっくりと言葉を続けた。 「ええ。そして、その『表見代理』は、あなたの会社を『地雷原』に立たせる、非常に危険な概念になり得ます。本来であれば無効になるはずの契約が、有効と見なされてしまう可能性がある。これはスタートアップにとって、致命的なリスクになりかねません」俺は、神崎さんの言葉に、全身から血の気が引くのを感じた。俺の一言が、会社を破滅させる地雷だったなんて。
セクション3: 神崎の法務解説(最重要・解説部)
【神崎の法務レクチャー】
「青木さん。まずは『代理』という概念から整理しましょう。私たちがビジネスを行う上で、全ての契約行為や意思表示を社長一人で行うのは不可能です。だからこそ、誰かに『代わりにやってもらう』必要が出てきます。これが『代理』です」
神崎さんはホワイトボードに図を書き始めた。
「代理の基本的な構造は、本人(ビジラボ)、代理人(斉藤さん)、相手方(大家さん)の三者関係です。本人が代理人に『代理権』を与え、代理人がその権限の範囲内で相手方と契約を結ぶ。そうすると、その契約の効果は直接本人に帰属します。つまり、斉藤さんが結んだ契約であっても、法的には青木さん(ビジラボ)が結んだのと同じ扱いになる、ということです」
「なるほど…まあ、それは分かります。俺が『これお願い』って斉藤に頼んだら、その結果は俺に来る、ってことっすよね」
「ええ、その通りです。そして、その『代理権』が発生するには大きく二つのパターンがあります。一つは青木さんのように、本人が意思表示をして与える『任意代理』。もう一つは、未成年者の親権者のように、法律によって自動的に与えられる『法定代理』です。今回は、青木さんが斉藤さんに依頼したという点で、『任意代理』が問題になっています」
「でも、俺はオフィス契約の代理権なんて与えてないっすよ!」
「そうですね。しかし、問題はまさにそこから発生します。もし代理人が、本人から与えられた『代理権の範囲を超えて』行為をしてしまったり、そもそも『代理権を持っていないのに』代理行為をしてしまったりした場合、どうなるでしょうか。これを『無権代理』と言います」
【神崎の補足解説】無権代理(むけん_だいり)とは?
代理権がないにもかかわらず、本人の代理人として契約などの法律行為を行うことです。原則として、その行為は本人に対して効果を生じません。つまり、本人に責任は発生しない、というのが大原則です。
「無権代理は、原則として本人には効果が及びません。つまり、無効ということです。ですが、それだと取引の相手方が困りますよね?斉藤さんが『青木の代理人だ』と言って契約したのに、後で『やっぱり無効でした』では、相手方は信用して契約できません。そこで民法は、相手方の保護と取引の安全を図るために、本人に『追認』の機会を与えています。青木さんが、その契約を後から『やっぱり有効にします』と認めることですね。追認すれば、その契約は有効になります。また、相手方には『催告権』や『取消権』があり、契約をどうするかを本人に迫ることも可能です」
俺は少し安心した。無効なら、まあ大丈夫だ。
「…と、ここまでは一般的な『無権代理』の話です。しかし、青木さんのケースで、より深刻な問題となるのは『表見代理』という概念です。これが、地雷の本体と言えるでしょう」
神崎さんの言葉に、俺の安心感は一瞬で吹き飛んだ。
【神崎の補足解説】表見代理(ひょうけん_だいり)とは?
代理権がないにもかかわらず、その行為を本人に帰属させることで、取引の安全を保護する制度です。本人が、まるで代理権を与えたかのような「外形」を作ってしまった場合、相手方がそれを信じることに無理がない限り、本人はその代理人の行為について責任を負わなければなりません。
「表見代理が成立するパターンはいくつかありますが、今回、青木さんのケースで最も懸念されるのは『代理権授与の表示』です。つまり、あなたが斉藤さんに『片腕だ』とか『任せる』『俺が責任を取る』と、明確に言ったことです」
「でも、俺は利用規約のチェックを任せただけで、オフィス契約なんて…!」
「ええ、そうかもしれません。しかし、大家さんから見ればどうでしょう?『社長が「何でも任せる、責任は取る」と言っていた。そして、いつも社内の手続きを代行している斉藤さんが、社長の代理人としてサインをした』。この状況で、大家さんが斉藤さんを『社長の代理人ではない』と疑うことは、果たして容易でしょうか?」
神崎さんの問いに、俺は言葉を失った。確かに、いつも「俺の片腕」と公言し、実際に多くの業務を任せていた。大家さんも、俺たちがバタバタしている様子を普段から見ていたはずだ。
「つまり、青木さんの言動によって、斉藤さんに代理権があるかのような『外形』が作られてしまった、ということです。そして、相手方である大家さんは、その『外形』を信じて、斉藤さんに代理権があると『善意』で『過失なく』信じてしまった。この場合、民法は、外形を作った本人、つまり青木さん(ビジラボ)に責任を負わせる、と判断する可能性が高いのです」
「う、嘘だろ…。俺が責任を取らなきゃいけないってことっすか?俺が頼んでもない契約について…」
「ええ。それが『表見代理』の恐ろしいところです。本人が意図せずとも、その言動が第三者から見て代理権があるように見えれば、本人は責任を負わざるを得ない。これは取引の安全を守るための非常に重要なルールであり、同時に経営者にとっては地雷となり得るものなのです。特にスタートアップでは、社長が多忙なあまり、社員に曖昧な指示を出しがちです。それが、こうした思わぬリスクに繋がることが非常に多い」
神崎さんはさらに、「支配人」という概念についても言及した。
「ちなみに、商法には『支配人』という特別な代理人の制度もあります。支配人は、本社の営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持つ、非常に広範な代理権を持つ者です。支配人を選任した場合は、その旨を登記する必要があります。登記されている支配人が行った行為は、たとえ本人(会社)がその行為を望んでいなくても、原則として会社が責任を負います。これも、代理制度の一種であり、外部から見て責任の所在を明確にするための制度です」
【神崎の補足解説】支配人(しはいにん)とは?
商法で定められた、商人の営業に関する包括的な代理権を持つ使用人です。支店長などがこれに該当することが多く、その権限は非常に広範で、登記することで公示されます。登記された支配人が行った行為は、会社にその責任が帰属します。
「今回の斉藤さんは『支配人』として登記されていたわけではありませんが、あなたが普段から斉藤さんを『俺の片腕』『何でも任せる』と公言し、実際に多くの業務を委ねていたことで、外部からは『事実上の支配人』のように見えてしまうリスクがあった、ということです」
俺は、自分の軽率な言動が、こんなにも大きなリスクをはらんでいたことに、ただただ愕然とした。
セクション4: 青木の理解と葛藤(発展部)
「要は、俺が『斉藤に代理権を与えた』と明確に言ってなくても、俺の普段の言動や、斉藤にやらせてた業務の範囲が広かったことで、大家さんは『斉藤は俺の代理人だ』って信じちゃったってことっすか? で、たとえ俺が頼んでないオフィス契約にサインしても、俺が責任取らされる可能性がある、と…」 俺は必死に、神崎さんの話を自分の言葉で言い換えようとした。頭の中がグチャグチャだ。 「その通りです、青木さん。まさに『青木さんのせいでそう見えた』という点に、あなたの『帰責性』が認められるわけです。そして、相手方である大家さんが『斉藤さんにはオフィス契約を結ぶ権限がない』と知っていたり、知るべきだったりすれば表見代理は成立しませんが、そうでなければ、会社が責任を負うことになります」 「うおおお、ヤバい!マジでヤバいっすね…。じゃあ、これからどうすればいいんすか?斉藤に何も任せられなくなっちまう!」 俺は頭を抱えた。斉藤に何も任せられないとなると、俺の業務はさらにパンクしてしまう。 「青木さん、落ち着いてください。重要なのは、『代理権の範囲を明確にする』ことです。例えば、斉藤さんに『サービス利用規約のチェックと、その変更の社内手続きは任せるが、契約書への最終サインは社長である私が行う』というように、具体的な権限の範囲を書面で明示しておく。そして、それを関係者にも伝えておく、ということが重要です」 神崎さんの言葉に、俺はハッとした。書面。そうか、口約束ではなく、書面で明確にするのか。 「前に『権利能力』や『行為能力』の話もしましたよね。誰が契約の主体になれるか、誰がまともな判断能力を持っているか。それに加えて、『誰がどこまでの権限で何をできるか』というのも、同じくらい、いや、それ以上に重要なんですね…。俺は、斉藤が優秀だからって、丸投げしすぎてたんだ…」 俺は斉藤を振り返った。斉藤は、まだ不安そうな顔で俺を見ている。申し訳ない気持ちと、自分の軽率さへの苛立ちが混じり合う。 「ビジラボは成長期に入り、業務はますます複雑になります。今後、田中さんも含め、チームメンバーに権限を委譲していく場面は増えるでしょう。その際、誰にどの範囲の代理権を与えるのか、そして与えない権限についてもしっかりと線引きをする。これが、未来のトラブルを未然に防ぐ、経営者の重要な責務です」 「…はい。俺、甘かったっす。まさか、俺の『任せる』の一言が、こんな地雷になるとは…。でも、神崎さんの話を聞いて、少しだけ光が見えてきた気がします。これからは、もっと権限の委譲について、法的にしっかり考えるようにします」 俺は拳を握りしめた。情熱と勢いだけでは、会社は守れない。俺は、法務という名の「地雷原」を、一つずつ慎重に、しかし着実にクリアしていくしかないのだ。セクション5: 解決への一歩と小さな成長(結論部)
オフィス契約の件は、すぐに大家さんに連絡を入れ、俺が直接交渉し直すことになった。幸い、まだ引っ越しまで時間があったのと、大家さんもさすがに「社長本人の意思と異なる契約」という点に多少は配慮してくれたため、修正に応じてもらえることになった。ホッと胸をなでおろす。今回の件で、俺は一つ大きな教訓を得た。 「斉藤、本当にすまなかった。俺の曖昧な指示のせいで、お前を危険な目に遭わせてしまった」 「いえ、社長…。私も、もっと確認すべきでした」 斉藤はまだ恐縮していたが、俺はもう逃げない。 「いや、俺の責任だ。これからは、お前に何かを頼む時は、必ず書面で、何ができて、何ができないかを明確にする。そして、社外の人にもそのルールを共有する。権限委譲は重要だけど、曖昧さは会社の命取りになるってことが、今回の件で本当によく分かった」 斉藤は、少しだけ安堵した表情を見せた。 「そうですね。明確なルールがあれば、私も安心して業務に取り組めます」 俺は、神崎さんが去った後、改めて斉藤と今後の業務分担と権限範囲について話し合った。 「法務、マジでヤバいけど、やるしかねぇ…。俺が会社を守るんだ!」 俺は、新たな地雷を踏まないために、もっと賢く、もっと強くならなければならないと、改めて決意したのだった。ビジラボは、まだ始まったばかり。俺たちの法務奮闘記も、まだまだ序章に過ぎない。
2. 記事のまとめ (Summary & Review)
📚 今回の学び(神崎メンターの総括)
[学習ポイント1]: 「代理」とは、本人の代わりに代理人が法律行為を行い、その効果が直接本人に帰属する制度である。ビジネスの効率化に不可欠だが、その権限範囲の明確化が極めて重要。
[学習ポイント2]: 「無権代理」は、代理権がない者の代理行為で、原則として本人に効果は及ばないが、本人の「追認」により有効となることがある。
[学習ポイント3]: 「表見代理」は、本人が代理権を与えたかのような「外形」を作ってしまった場合、相手方が善意無過失であれば、たとえ代理権がなくても本人が責任を負う。特にスタートアップの社長の曖昧な言動がリスクとなる。
[学習ポイント4]: 「支配人」は商法上の包括的な代理権を持つ者で、登記によりその権限が公示される。
今週のリーガルマインド(神崎の教訓) 「信頼できるパートナーでも、法的な権限の範囲は明確にしてください。曖昧な『信頼』は、いつか会社を飲み込む『ブラックホール』となり、取り返しのつかない損害を引き起こします。言動には、常に法的な責任が伴うことを忘れないでください。」
💭 青木の気づき(俺の学び)
- 「俺の『任せる』の一言が、まさかこんなデカい地雷になるとは…。斉藤は俺の右腕だけど、法的に見たら『何でもできる』わけじゃないんだ。これからは、誰に何を、どこまで任せるのか、書面で明確にしないとダメだ。口約束はマジで危険すぎる。情熱だけじゃ会社は守れねぇ、マジで。」
3. 次回予告 (Next Episode)
無事にオフィス契約の危機を乗り越えた俺は、改めて権限委譲の重要性を痛感した。会社の成長のためには、もっと明確なルールが必要だ。俺は、神崎さんのアドバイス通り、改めて会社の設立時に作った「定款」を見直そうと決意する。しかし、その「定款」の中身を見て、俺はまたしても頭を抱えることになる。「これ、誰が作ったんだ…?」
次回: 第6回 会社設立のバイブル! 「定款」って何を決めるの?